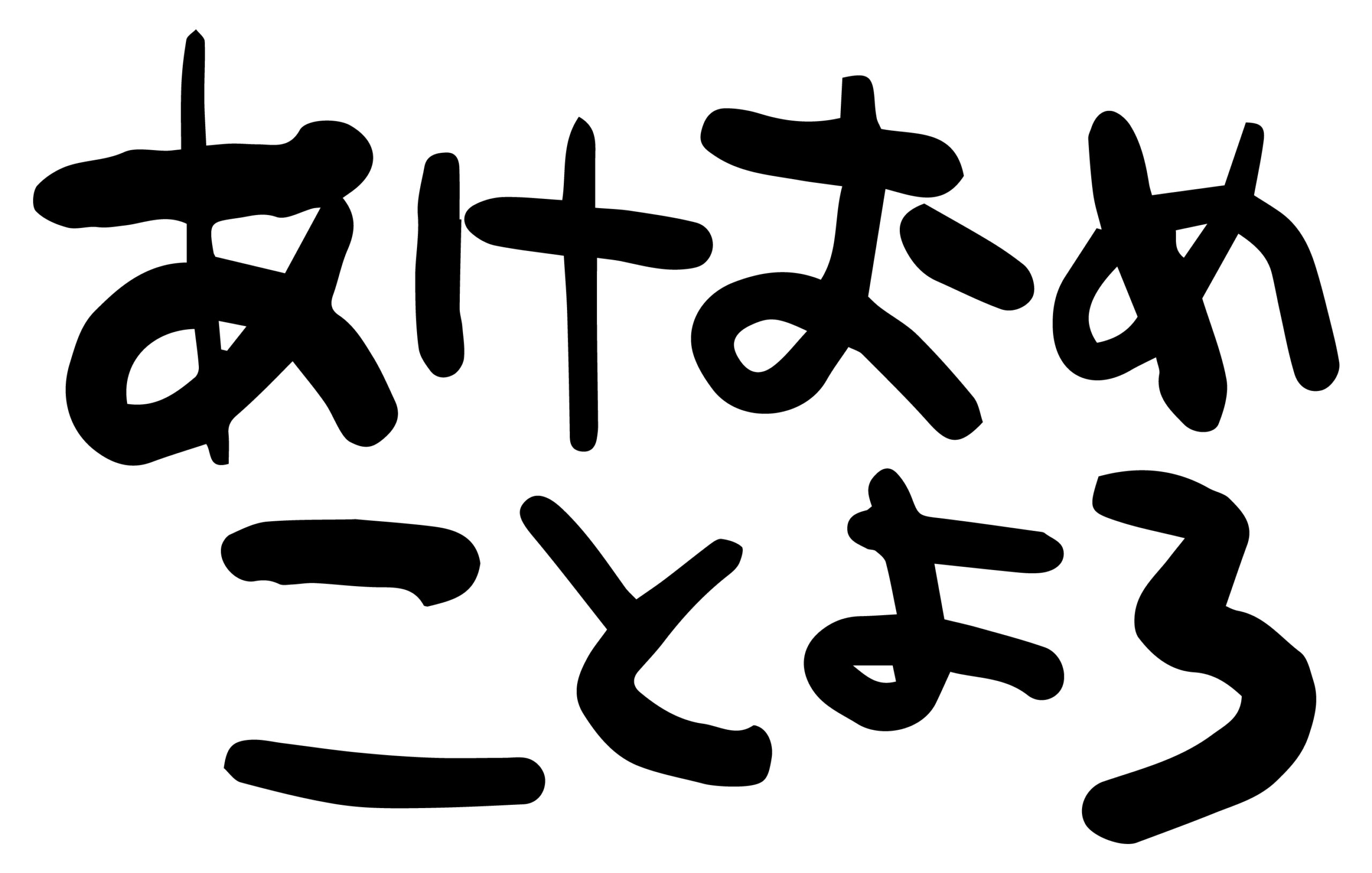新年が始まると、多くの人が「明けましておめでとうございます」と挨拶を交わしますが、この言葉をいつまで使ってよいのか疑問に思うことがあります。
特に挨拶が遅れた場合、それが失礼にあたらないか心配になることもあるでしょう。
この記事では、「明けましておめでとうございます」という挨拶がいつまで適切なのか、また正月の初めにLINEやビジネスメールでの挨拶のタイミングについて解説します。
「明けましておめでとうございます」の意味と使える期間

「明けましておめでとうございます」とは、新たな年を迎えたことを祝う挨拶です。
伝統的には、小正月の1月15日まで新年の挨拶を行うことが一般的でしたが、現代では「松の内」とされる1月7日までが普通です。
地域による違い:
以前は年賀状を12月25日までに投函すると元日に届きましたが、今はメールやLINEを使って新年の挨拶をすることが多く、挨拶を忘れがちです。
現在では、松の内は1月1日から1月7日までとされていますが、関西地方では松の内が1月15日までだった歴史があります。
さらに、鏡開きを1月20日に行う地域もあり、その日までなら挨拶が遅れても問題ないとされる場合もあります。
しかし、一般的には1月7日までが挨拶の期限とされており、大阪や京都の友人であってもその期限が一般的です。商売をしている家系でなければ、普通に1月7日までのルールを守ることが推奨されます。
ビジネスの場合、新年の挨拶は自社の初出社日から始めるのが通例で、遅くともその2日以内には行うことが望ましいです。
LINEで「あけましておめでとうございます」は何時に送るべき?

「あけましておめでとうございます」というLINEを送る適切な時間帯については、年明け直後の1月1日が一般的ですが、いつまでも問題なく送れるわけではありません。
新年の挨拶はタイミングが重要で、特に元旦はいつLINEを送るかが考慮されます。
多くの人が新年の午前中を寝て過ごすため、遅すぎる挨拶は「忘れていたのでは?」と受け取られかねません。
具体的には、1月1日の午前中、特に11:30までにLINEでの挨拶を済ませることが望ましいです。
夕方や翌日になると適切な時間帯ではなくなります。
新年のカウントダウン直後、つまり0:00から0:30頃にLINEを送ることも一般的です。
親しい友人や恋人なら、もし相手が寝ていても問題にはなりにくいでしょう。
特に25歳以下の若者同士では、このような時間帯でも受け入れられやすいと言えます。
しかし、25歳を超えると、元旦の午前中に挨拶を送るのが一般的に良識とされます。
特に45歳以上の人々は早寝の傾向にあるため、深夜のLINEは避けた方が無難です。それにより相手を不快にさせることなく、新年の挨拶をスムーズに行うことができます。
1月2日や3日に「あけましておめでとうございます」を送るのは問題なし?それとも失礼?
元旦を逃してしまい、1月2日や3日に新年の挨拶を送ることがあるかもしれません。
この場合、遅れてしまった挨拶をどう受け止めるかは、受け取る側の寛容さに依存します。友人や知り合いから遅れた挨拶が届いた時には、怒ることなく受け入れるのが最善の対応です。
新年に遅れて挨拶することで不快に思う人もいますが、正月の精神に反して、遅れた挨拶でいらだつのは避けるべきです。
実際、正月には喧嘩を避けるというルールがあります。挨拶が遅れたことを責めるよりも、新年を迎えられたこと自体を祝う心持が大切です。
もし1月2日や3日に「あけましておめでとうございます」という挨拶に怒る人がいるなら、その人との関係を見直すことも考えるべきです。
正月は多忙を極める時期であり、全ての人が1月1日に挨拶を完了できるわけではありません。
「あけおめ、ことよろ」の語源とは?

「あけおめ、ことよろ」という挨拶は、どのようにして生まれ、普及したのでしょうか。
このフレーズは1996年にインターネットのチャットで使用され始めたとされています。
インターネットとパソコンが普及する中で、短縮された挨拶が流行りました。
「あけおめ、ことよろ」という言葉は、その後1999年の大晦日にテレビ番組で使用されたことが広く認知されるきっかけとなりました。このフレーズは今でも使用されていますが、その起源や流行の背景を知ることは、言葉の変遷を理解する上で興味深いかもしれません。
※補足
「あけおめ、ことよろ」というフレーズが広く知られるようになったのは、1999年の大晦日のテレビ番組『CDTVカウントダウンライブ』で歌手の持田香織が使用したことがきっかけです。この表現自体は1996年頃から存在していましたが、テレビでの使用によって一般に広まり始めたと言われています。
最後までお付き合いいただきありがとうございました。