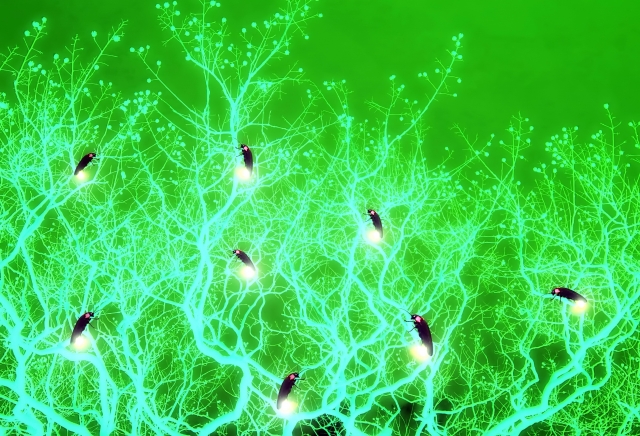「蛍の光」は日本のお店が閉店する時間や卒業式など、終わりや別れの時によく耳にする曲です。
この曲が大晦日や新年に歌われる背景と、その歌詞の意味について解説します。
「蛍の光」の起源
この曲の正式な読み方は「ほたるのひかり」です。
原曲はスコットランドの民謡「Auld Lang Syne(オールド・ラング・サイン)」で、「懐かしい昔」を意味します。
788年にスコットランドの詩人ロバート・バーンズが既存の民謡に基づき作詞しました。
内容は、古い友人との再会と過去の思い出を語り合いながら祝杯をあげるというものです。
スコットランドではこの曲が国民的な愛唱歌として、重要な行事で歌われます。
簡単な解説は下記のとおりです。
古い友人は忘れていくものなのだろうか
古い友人は心から消え果てるものなのだろうか
あの懐かしい日々を君は覚えているだろうか
友よ、懐かしい日々のために、親愛のこの一杯を飲み干そうではないか
僕ら二人は丘を駆けまわり、可憐な雛菊(ひなぎく)を摘んだ
しかし、懐かしい日々は過ぎ去り、僕らはさまよっていた
僕ら二人は朝から晩まで小川で遊んだ
しかし、僕ら二人を隔てた海は広く荒れている
今ここに、僕の親友の手がある!さあ、握手をしよう!
今僕らは、友情の杯を飲み干そう、懐かしい日々のために
素敵な歌詞ですね。
日本への伝来は明治時代にアメリカ経由で行われ、「小学唱歌集初編」で「蛍の光」として1881年に発表されました。作詞は稲垣千穎が担当しました。
この曲の日本語歌詞の「蛍の光、窓の雪」は「蛍雪の功」という成語が元となっています。
これは、努力して学問に励むことを表します。故事によると、中国晋時代に車胤と孫康という二人の青年が、家が貧しく灯油を買えないため、蛍の光や雪明かりを利用して学問に励み、最終的には成功を収めました。
「蛍の光」が新年に歌われる理由として、日本では大晦日に、海外では新年の瞬間に、それぞれ新しいスタートと終わりを象徴として歌うからです。
解説「蛍の光」の詞の内容

「蛍の光」の歌詞は、学びと努力を象徴する内容で綴られています。
この曲は、学問を続ける中で直面する困難と挑戦を乗り越え、成果を得るというメッセージを伝えています。その具体的な詞の内容とその意味について解説します。
1番
蛍の光 窓の雪
書読む(ふみよむ)月日 重ねつつ
何時(いつ)しか年も すぎの戸を
開けてぞ今朝(けさ)は 別れ行く
2番
止まるも行くも 限りとて
互に(かたみに)思ふ 千万の(ちよろずの)
心の端を(はしを) 一言に
幸くと許り(さきくとばかり) 歌ふなり
3番
筑紫の(つくしの)極み 陸の(みちの)奥
海山遠く 隔つ(へだつ)とも
その真心は 隔て無く
一つに尽くせ 国の為
4番
千島の(ちしまの)奥も 沖繩も
八洲の(やしまの)内の 護り(まもり)なり
至らん国に 勲しく(いさおしく)
努めよ我が兄(せ) 恙無く(つつがなく)

『いつしか年も「過ぎ」のとを』ではなく、
『いつしか年も「杉の戸」を』だったのですね。
これ以外にも改めて見ると、間違って解釈している部分が結構ありました。
以下に解説します。
1番:
書物を読むために蛍の光や月の明りを使いながら過ごした日々が流れ、いつの間にか多くの時間が過ぎ去ります。今日、杉で作られた戸を開けて、学びの場を離れ、クラスメイトと別れを告げます。この部分で「過ぎ」と「杉」を掛けた言葉遊びが含まれています。
2番:
故郷に残る者も、去る者も今日で別れが訪れます。何千もの深い感謝と思い出を胸に、ただ一言、「幸あれ」と願いを込めて歌います。
3番:
地理的な隔たりがあっても、九州の端から東北の深い所まで、海や山に囲まれた遠く離れた場所でも、その真心は変わらず、国のために力を尽くすよう歌っています。
4番:
千島列島から沖縄に至るまで、日本の重要な地域を詠み、海外の領域にもその勇気と力を示すよう呼びかけています。これもまた、無事であることを願っています。
現在よく聞かれるのは1番と2番で、特に卒業式などの別れの場面で感慨深く歌われます。
3番と4番は、その地域の役割を果たし国を支える内容で、明治時代の軍国主義的な背景が色濃く反映されていましたが、戦後はそのような内容の歌詞は避けられるようになりました。
「蛍の光」が卒業式に採用され始めたのは1882年7月、東京女子師範学校の卒業式が最初で、1890年頃からは多くの学校で卒業式の定番曲として定着しました。
この伝統は大日本帝国海軍の教育機関でも引き継がれました。
大晦日に「蛍の光」を歌う理由
「蛍の光」は、大晦日のNHK紅白歌合戦で伝統的に歌われますが、その背景にはどのような理由があるのでしょうか?
1949年(昭和24年)に公開された映画「哀愁」では、大尉と踊り子の切ない恋物語が描かれ、「Auld Lang Syne」が「別れのワルツ」として使用されました。
この曲は映画の影響で強い印象を残し、日本でも広く認識されるようになりました。また、この曲と「蛍の光」は、それぞれが異なる拍子を持つものの、似た旋律を持っているため混同されやすくなりました。
映画「哀愁」では、閉店時間のシーンで「別れのワルツ」が流れ、大尉と踊り子が別れる様子が描かれています。この美しいが悲しいシーンは、映画史に残るほど印象的でした。
この影響で、「別れのワルツ」および「蛍の光」は閉店時間や特定の別れの場面で使用されるようになりました。
日本では特に「蛍の光」が大晦日に歌われるようになり、年の終わりという「別れ」の象徴として定着しました。
なぜ海外では新年に歌われるのか
海外では「Auld Lang Syne」が新年を迎える瞬間に歌われることが多いです。
英語圏では結婚式や誕生日、クリスマスなど様々な節目で歌われ、新年のカウントダウンで「新年おめでとう」と祝福する際にも用いられます。
これは、歌が新たな始まりや友情の継続を祝う意味を持つためです。
まとめ
いかがでしたか、「蛍の光」はスコットランドの民謡が原曲であり、その楽しい歌詞とは対照的に、日本では物悲しいイメージで受け取られることが多いです。
文化的な背景や受け取り方の違いが、同じ曲でも異なる感情を呼び起こす理由として挙げられます。この記事を通じて、その理由について理解を深めることができると嬉しいです。