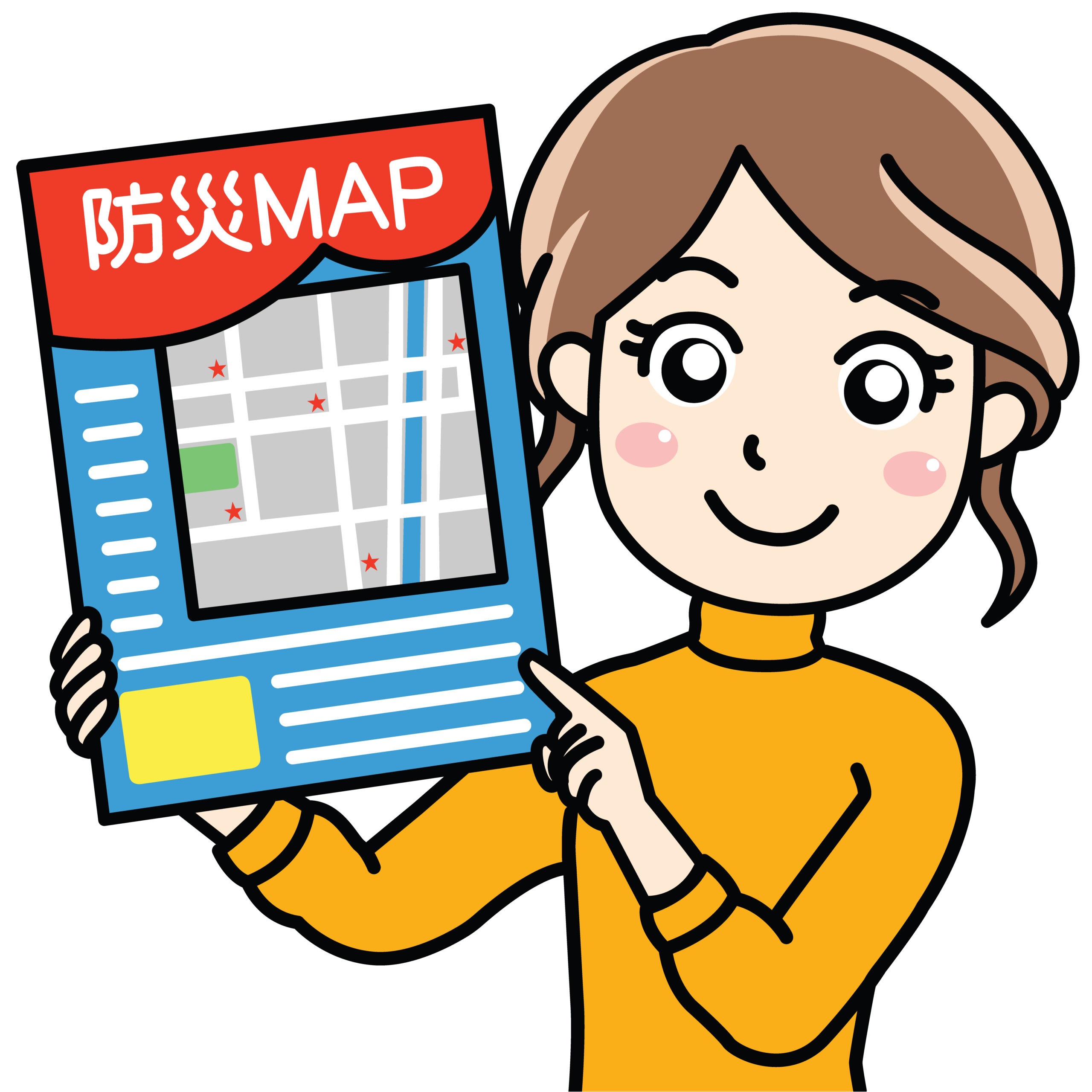防災マップとハザードマップという言葉を耳にしたことがあるけれど、具体的にどのようなものかよく分からないという方も多いのではないでしょうか。
これらのマップにはどのような違いがあり、どこをチェックすべきなのか、災害に備えるために重要なポイントを詳しくご紹介していきますね。
防災マップとハザードマップの違い
防災マップとハザードマップの大きな違いは、提供される情報の内容にあります。
防災マップは、災害が発生した際に「避難するためのルート」や「避難所・避難場所」の情報をまとめたもので、主に安全な避難行動をサポートするためのツールです。
一方、ハザードマップは、特定の地域における災害の発生リスクや被害が想定されるエリアを示したものです。
つまり、避難先やルートを確認したい場合は防災マップ、災害のリスクを把握したい場合はハザードマップを活用するのが適切です。
防災マップとは?チェックすべきポイントと入手方法

防災マップは、各自治体(市区町村)が作成し、公式サイトやパンフレットなどの紙媒体で提供されます。
ここには、地域ごとの避難ルートや避難所の情報が記載されており、地震、台風、土砂災害などの災害種別に関係なく、指定された避難場所を確認することができます。
自治体によっては、避難場所の情報に加え、危険とされる地域についても一部記載されていることがあります。
また、自治体の情報に加え、「Yahoo!防災速報」など、信頼性の高い企業が提供する防災アプリやサイトも活用できます。
災害に関する情報を得る際には、まず自治体の公式情報を確認し、次に信頼できる大手の情報源を参考にすることが重要です。
SNSを利用して情報を収集することも可能ですが、発信元が不明確なケースも多いため、常に「一次情報」、つまり公式機関が発信する内容を優先してチェックすることをおすすめします。
「防災マップの重要ポイント」避難場所と避難所の違いを知ろう!
防災マップには、例えば「山田公民館(住所:山田市伊藤町1-1-1、電話番号:XXX-XXXX-XXXX)」といった情報のほか、避難できる屋内・屋外の施設が明記されていることが一般的です。
防災マップの内容とは?
防災マップには以下の情報が記載されています:
- 施設名(例:公民館、学校など)
- 住所(具体的な所在地)
- 連絡先(緊急時の確認用)
- 避難施設の種類(屋内・屋外) ← ここがポイント!
防災マップと聞くと「地図」をイメージしがちですが、実際は「避難施設のリスト」としての側面が強く、各施設の名称や連絡先が一覧として整理されています。
多くの自治体では、「屋内:体育館、屋外:グラウンド」といったように、避難施設の種類が明記されています。
例えば、屋根のある屋内避難所であれば、早めに避難することで天候の影響を受けにくくなります。
特に長期的な避難を想定する場合は、屋内施設を優先的に確保することが重要です。また、避難所は先着順で利用されることが多いため、迅速な避難が求められます。
避難場所と避難所の違いを理解しよう
「避難場所」と「避難所」という言葉は似ていますが、実際には役割が異なります。
つまり、避難場所は緊急時に身の安全を守るために利用するもので、一定の危険が去った後は別の場所に移動する必要があります。
一方、避難所は災害が終息するまで滞在し、日常生活が継続できる環境が整えられています。
簡単に言えば、「避難場所=一時的な安全確保」「避難所=生活を守る施設」と考えるとわかりやすいでしょう。
避難のポイント
避難する際には、可能であれば避難所を優先して確保することをおすすめします。なぜなら、避難場所では基本的に一時的な避難しかできず、生活のための設備が整っていないからです。状況に応じて、どちらの施設を利用するのかをあらかじめ確認しておくことが重要です。
防災マップの入手方法:手軽に探すコツを紹介!

防災マップを手に入れるには、各自治体の公式ウェブサイトからダウンロードするのが最も一般的な方法です。
しかし、自治体のホームページにはさまざまな情報が掲載されているため、「どこに防災マップがあるのか分からない…」と困ることもありますよね。
そこで、簡単に見つけるための方法をご紹介します。
防災マップを見つける方法
防災マップを探す際のおすすめの手順は、Google検索を活用することです。
検索バーに「市区町村名+防災マップ」と入力すると、多くの場合、検索結果の上位に自治体の防災マップページが表示されます。
例えば:
- 大都市の場合(例:東京、名古屋)
- 正規の自治体サイトは「都市名.lg.jp」のドメインを使用。
- 例:「東京都の場合 → map.bosai.metro.tokyo.lg.jp」など。
- 地方都市の場合(例:高岡市、盛岡市)
- 「city.都市名.県名.jp」のドメインが公式の証拠。
- 例:「富山県高岡市 → city.takaoka.toyama.jp」など。
正しいサイトを見分けるポイント
検索結果には、時折民間企業が提供する防災関連の情報も含まれますが、信頼できる情報を得るためには、以下のドメインを目安にしてください。
- 「.lg.jp」ドメイン:全国の都道府県・市区町村の公式サイト(例:大阪府)
- 「city.○○.○○.jp」ドメイン:地方自治体の公式ページ(例:高岡市)
これらのドメインを確認することで、誤った情報に惑わされることなく、確実に最新の防災マップを手に入れることができます。
まとめ
防災マップを素早く入手したい場合は、以下の手順を試してみてください。
- Googleで「市区町村名+防災マップ」を検索。
- 検索結果の上位に表示される「.lg.jp」または「city.○○.○○.jp」のドメインをチェック。
- 各自治体の防災ページから最新のマップをダウンロード。
これらのポイントを押さえておけば、災害時の備えとして必要な情報をスムーズに入手できます。
最後までお付き合いいただきありがとうございました。