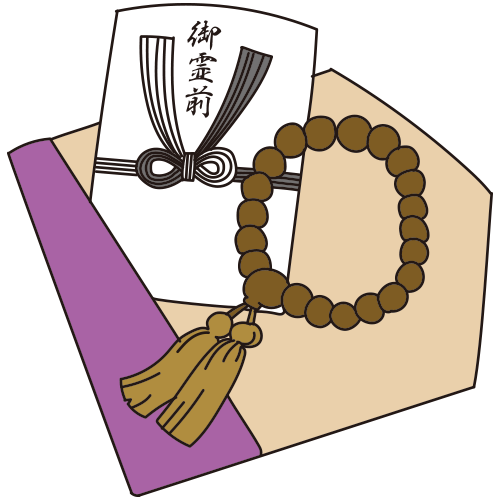訃報を受け取るのはいつも心が重くなります。
年配の方々は過去に何度か葬儀に出席された経験がおありでしょう。
しかし、若い方々にとっては、まだそうした経験が少なく、葬儀の進行や作法が未知のものかもしれません。
本記事では、「お通夜」と「お葬式(葬儀・告別式)」の違いについて解説し、これらの儀式で何が行われ、参列者としてどのような行動を取るべきかを説明します。
事前に流れを理解しておくことで、経験が少なくても安心して式に臨むことができます。
お通夜とお葬式(葬儀・告別式)の違い

誰かが亡くなると、以下の儀式が執り行われます。
– お葬式(葬儀・告別式)
通常、お通夜は亡くなった翌日の夕方に開始されますが、予期せぬ不幸のため、日程が前後することもあります。
これまでの経験から、お通夜は故人が亡くなった当日、または2-3日後に行われることがありました。
お通夜では、故人と親しかった人々が集まり、最後のお別れをします(通常1時間から1時間30分程度)。
かつては親しい人だけが参列する私的なものでしたが、最近ではそれほど親しくない人も参列することが一般的です。
参列者が帰宅した後、喪主と家族は一晩中、ろうそくとお線香を灯し続けながら故人と共に過ごします。
翌日の午前中には、お葬式(葬儀・告別式)が行われます。
これはお通夜の次の日に行われ、葬儀と告別式が一体となった儀式です。
僧侶による読経、参列者の焼香、そして出棺が行われ、ここで参列者は散会し、親族は火葬場へと向かいます。
お通夜と葬儀の手順とその違い
まず、お通夜と葬儀の基本的な流れの違いを概説した後、具体的な手順について詳しく説明します。

お通夜の進行
【通夜法要の進行】約1時間〜1時間半
1 僧侶による読経
↓
2 遺族・親族の焼香
↓
3 弔問に訪れた一般参列者の焼香
↓
4 僧侶による説法
↓
5 喪主の挨拶
↓
6 通夜ぶるまい(簡単な食事や飲み物が提供される。一般参列者には通常提供されません)
通夜に参加する際、上記の手順で進行されることが多いです。
式場のスタッフが案内するので、その指示に従うだけで問題ありません。
焼香を行う以外は、ほとんど座っているだけで良いので、故人とのお別れを静かに行ってください。
通夜ぶるまいは近年、遺族のみで行うことが多くなっており、一般参列者はそれ以前に退席することが一般的です。
葬儀(葬式)の進行
お通夜の翌日に葬儀が行われます。
「葬儀」とは故人をあの世に送る儀式と、参列者が故人とお別れする告別式を指します。
現在はこれらを区別せず、一連の流れで行われることが一般的です。
【葬儀・告別式の進行】約2時間
1 僧侶による読経
↓
2 遺族・親族の焼香
↓
3 一般参列者の焼香
↓
4 弔辞や弔電の紹介
↓
5 喪主の挨拶
↓
6 遺族が故人と最後のお別れをし、棺に花を飾る
↓
7 出棺 棺が霊柩車に移され、喪主から挨拶が行われる
↓
(この時点で一般参列者は帰宅します)
この後、遺族と近親者だけが火葬場へ向かい、火葬、骨拾い、初七日法要、精進落としを行います。
一般参列者は焼香と喪主の挨拶までが主な参加内容で、遺族の最後のお別れは遠くから見守ります。
出棺の際は、故人と喪主・親族が火葬場へ向かうのを見送り、これが最後のお別れとなります。
通夜と葬式の参加判断ガイド

訃報をうけた際、参加すべきか迷うのが通夜と葬式です。
一般的に、通夜は親族や非常に親しい友人のために、葬式は広く一般に開かれる儀式とされていますが、最近ではこの区分が曖昧になっています。
特に、親しくない関係であれば、夜に行われる通夜への参加が増えています。
これは、参加しやすいからでしょう。
しかし、最も重要なのは、故人に対する想いを形にすることです。
ですから、どちらか一方に参加するだけでも問題ありません。
親しい人の場合は、できれば両方に参加することが望ましいでしょう。
個人的な経験からも、親族が亡くなった際は通夜と葬式の両方に出席しています。
一方で、それほど親しくない知人や友人の親の場合は、通夜だけに参加しています(スケジュールが合わない場合は除く)。
年代が近い友人の場合でも、親しさに応じて参加を決めています。
親しい友人であれば両方、そうでなければ通夜のみにします。
まとめ
通夜と葬式の違いや式の内容について説明しました。
実際に参加経験がないと分からないことも多いため、これを参考にして備えてください。
一番近い人生の先輩の両親に聞くのもよいですね。
どちらに参加するにしても、故人への敬意を表し、遺族の方への配慮が最優先です。
何よりも、納得のいくお別れを心がけることが大切です。
最後までお付き合いいただきありがとうございます。