時折、ニュースで「暦の上では春」といった表現や「今日は夏至」という特別な言葉を聞くことがあります。
これらは、季節の変わり目を示す二十四節気に関連しています。
日本では、四季の存在が明確ですが、なぜさらに細かく季節を分けるのでしょうか?
二十四節気は、一年を二十四の時期に分割し、各時期が特定の季節変化を象徴します。
これには、それぞれの期間が独自の意味を持っていますが、これを全て覚えるのは少し大変です。
この記事では、二十四節気の意味、起源、覚え方、そして完全なリストを提供します。
「二十四節気の詳細な意味とは?」

二十四節気は、立春から始まり立冬に至るまで、年間を通じて24の重要な節目で構成されています。
これらは奇数番号と偶数番号のグループに分けられ、偶数番号のグループは「中気」として、季節の中心を示す時期を表し、暦上で「○月中」と記されます。
一方、奇数番号のグループは「節気」と呼ばれ、季節の始まりを示す時期であり、「○月節」として記載されます。
節気と中気は交互に現れ、太陰太陽暦(旧暦)の閏月の決定にも影響を及ぼしていました。
二十四節気の日付は年によって若干異なり、これは古代の暦法の精度を示しています。
起源は中国戦国時代にさかのぼり、日本では平安時代に伝わりました。
太陽暦が主流の現代でも、月の満ち欠けに基づく太陰暦がかつて使用されていました。
この暦は、新月から次の新月までを一月とし、月の長さが29日や30日で変わり、年間約355日で構成されていました。
太陽暦とのずれを修正するため、古代中国では太陰太陽暦が採用され、さらに精密な調整として二十四節気が考案されました。
太陽の見かけ上の運行を24等分し、各区切りに季節を象徴する名称を付けることで、暦と実際の季節感とのズレを矯正しました。
二十四節気は、単なる暦法に留まらず、自然と調和を図る古人の哲学が込められています。
季節の移り変わりを感じながら、私たちもその豊かなリズムに身を委ねるのはどうでしょうか。
「二十四節気の発音とその暦について」
二十四節気は、日本語で「にじゅうしせっき」と発音されます。
テレビなどで耳にする「暦の上では…」というフレーズは、現代のグレゴリオ暦(太陽暦)ではなく、かつて二十四節気を採用していた天保暦(太陰太陽暦)を指しています。
現在主流のグレゴリオ暦を新暦、天保暦を旧暦と呼びます。
新旧の暦は約1か月のずれがあるため、旧暦は新暦に比べて大体1か月早く進行します。
二十四節気の起源は、日本の東北地方と同じ緯度の中国黄河流域にあり、そのため、元々の気候感覚が日本のそれと異なります。
例えば、ニュースで「立春です」と報じられる2月初旬は、私たちが感じる冬の寒さがまだ続いている時期です。
季節の変わり目 四立と二至二分を探る
季節の変わり目を示す「四立」と「二至二分」は、日本の文化に深く根ざしています。ここでは、これらの季節の節目について詳しく説明します。
「四立」は立春、立夏、立秋、立冬の四つの季節の始まりを示します。
これらはそれぞれの季節がスタートする重要な日とされています。
たとえば立春は、冬の寒さが和らぎ始め、新たな春へと移行する時期を告げます。
この時期は、小寒や大寒から脱し、余寒見舞いへと移り変わります。
一方で、「二至二分」は冬至、夏至、春分、秋分を指し、これらは太陽の位置に基づく季節の節目です。
特に春分の日や秋分の日は彼岸の中日とされ、自然の変化が顕著に表れる時期です。
「暑さ寒さも彼岸まで」という言葉が示すように、これらの日を境に季節が大きく変わります。
四立と二至二分を理解することは、季節の流れと日本の自然、文化への理解を深める手がかりとなります。
日本の四季の美しさとその変化を感じ取ることが、文化を豊かにする鍵です。
二十四節気の完全ガイド
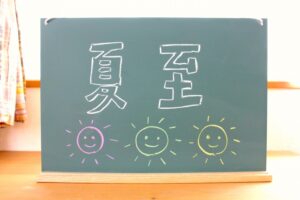
二十四節気は、年間を通じて24の異なる季節の区切りを示す名称で構成されています。
以下では、各節気の読み方、意味、および由来について解説します。
**立春(りっしゅん)**
– 日付:2月4日頃
– 概要:二十四節気の最初の節気であり、かつては新年の始まりとされていました。中国語の「立」には始まりの意味があり、立春は文字通り「春の始まり」を意味します。
**雨水(うすい)**
-日付:2月19日頃
-概要:この時期は、雪が雨に変わり始め、積もった雪が解け始めるころです。
**啓蟄(けいちつ)**
– 日付:3月6日頃
– 概要:「啓」は開くという意味で、「蟄」は土中の虫。この時期には、冬眠していた虫たちが地表に現れ始めることからその名がつけられました。
**春分(しゅんぶん)**
– 日付:3月21日頃
– 概要:昼夜の長さが等しくなる日で、ここから日が長くなることを意味します。春分は夏至、冬至、秋分とともに二至二分の一つです。
**清明(せいめい)**
– 日付:4月5日頃
– 概要:「清浄明潔」を略したこの言葉は、自然が清らかで明るい状態を指します。
**穀雨(こくう)**
– 日付:4月20日頃
– 概要:春の終わりに降る雨が農作物の成長を助けるため、「穀物に恵みの雨」という意味で穀雨と呼ばれます。
**立夏(りっか)**
– 日付:5月6日頃
– 概要:暦上で夏が始まる日です。立春、立夏、立秋、立冬は「四立」として知られ、四季の変わり目を示します。
**小満(しょうまん)**
– 日付:5月21日頃
– 概要:この時期、秋にまかれた麦が穂をつけ始めることから、作物が少し成長し始める様子を表します。
**芒種(ぼうしゅ)**
– 日付:6月6日頃
– 概要:「芒」は穂を指す言葉で、穀物の種まきの時期を象徴しています。

**夏至(げし)**
– 日付:6月21日頃
– 概要:北半球で日が最も長い日ですが、日本では梅雨の真っ只中にあたり、その感覚はぼやけがちです。
**小暑(しょうしょ)**
– 日付:7月7日頃
– 概要:梅雨明けが近づくとともに、本格的な夏の暑さが訪れます。この時期から立秋にかけての挨拶を「暑中見舞い」と言います。
**大暑(たいしょ)**
– 日付:7月23日頃
– 概要:一年で最も暑い時期が訪れます。立秋の前の18日間を「夏の土用」として、この期間中は特に暑さが厳しいとされます。
**立秋(りっしゅう)**
– 日付:8月7日頃
– 概要:この時期には暦上では秋が始まりますが、実際にはまだ暑い日が多く、この時期から残暑見舞いが始まります。残暑見舞いは一般的に立秋から白露の期間に行われます。
**処暑(しょしょ)**
– 日付:8月23日頃
– 概要:暑さのピークが過ぎ、次第に涼しさが増していく時期です。
**白露(はくろ)**
– 日付:9月8日頃
– 概要:朝晩の冷え込みが強くなり、植物の葉に露が現れ始める時期です。
**秋分(しゅうぶん)**
– 日付:9月23日頃
– 概要:昼夜の長さが等しくなる日で、この時期にはお彼岸があり、先祖供養として墓参りが行われます。
**寒露(かんろ)**
– 日付:10月8日頃
– 概要:露がより冷たくなり、朝晩の冷え込みが一段と強まる時期です。この時期には紅葉も始まります。
**霜降(そうこう)**
– 日付:10月23日頃
– 概要:寒さがさらに強まり、初霜が見られることもあります。この時期の風を「木枯らし」と称します。
**立冬(りっとう)**
– 日付:11月7日頃
– 概要:暦の上では冬が始まるこの日は、季節の変わり目を示します。
**小雪(しょうせつ)**
– 日付:11月22日頃
– 概要:寒さが徐々に厳しくなり、高地では雪がちらつき始める時期です。
**大雪(たいせつ)**
– 日付:12月7日頃
– 概要:雪が本格的に降り始め、一部地域では根雪となる時期です。
**冬至(とうじ)**
– 日付:12月22日頃
– 概要:北半球で最も夜が長くなる日で、伝統的にかぼちゃを食べたりゆず湯に入る風習があります。
**小寒(しょうかん)**
– 日付:1月5日頃
– 概要:寒さがさらに強まる時期で、この日を「寒の入り」と呼びます。
**大寒(だいかん)**
– 日付:1月20日頃
– 概要:年間で最も寒い期間であり、二十四節気の中で最後の節気です。次に訪れる立春に向けて、寒さはその頂点に達します。
二十四節気を効率的に記憶する方法

二十四節気の各名称を覚えるのは一見難しそうに感じますが、日常的によく聞く名称があるため、これらは比較的記憶しやすいでしょう。
特に、夏至や冬至、春分や秋分、そして立春、立夏、立秋、立冬のような節気は馴染み深く、これら八節を覚えることから始めると良いです。
さらに、「小暑と大暑」「小寒と大寒」「小雪と大雪」といった小と大のペアは覚えやすく、これにより14節気がカバーできます。
これで残りは10節気になり、より簡単に感じられるはずです。残る10節気は次のとおりです
– 啓蟄(けいちつ)
– 清明(せいめい)
– 穀雨(こくう)
– 小満(しょうまん)
– 芒種(ぼうしゅ)
– 処暑(しょしょ)
– 白露(はくろ)
– 寒露(かんろ)
– 霜降(そうこう)
これらを記憶する一つの方法は、語呂合わせを使うことです。
例えば「うすい(雨水)けいちゃん(啓蟄)は、せいめい(清明)に、こくる(穀雨)。しょう(小満)ぼう(芒種)しょ(処暑)は(白露)、かん(寒露)そう(霜降)。」といったフレーズを使うと覚えやすくなります。
まとめ(二十四節気の背景と意義)
二十四節気は、太陰太陽暦が使用されていた時代に、季節の感覚と暦のズレを矯正するために創設されました。
その起源は中国の黄河流域にあり、日本の気候とは完全に一致しない場合もありますが、古くから農作業のスケジューリングに利用され、生活に密接に関わる重要な要素でした。





















